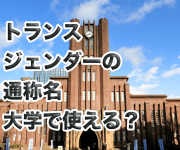封印されていた女性同士の恋愛
原作はパトリシア・ハイスミスの「The price of salt」。なんと1952年刊行というから驚き。
驚きというのは、60年以上も前の小説が映画化されたということではなく、1952年という時代に同性間の恋愛が描かれていたということ。
現在でこそ、街に出ればゲイバー、ビアンバー、ミックスバーやイベントなど、「わたしたち」にとって自分らしくいられる場所はたくさんあります。
この映画は女性同士の恋愛物語ですが、いかにこの時代ではそれが閉塞的で難しいことであったかがよく分かります。
ふたりの主人公
テレーズ ―殻に閉じこもる若き写真家

同僚に感じの悪い態度をとられても言い返せない。ランチのメニューも自分で決めることができない。撮った写真はシンクの下に隠したまま。結婚まで考えてくれている恋人がいるのに、なぜか情熱的になれない。決して不幸ではないけれど、どこか物足りない生活を送っていたテレーズ。
そんな彼女が、キャロルという女性に出会ったことで少しずつ自分を解放するようになります。部屋の壁に自分の作品を飾ったり、恋人に意見するようになります。まるで、水を得た魚のように生き生きとするのです。やっと本当の自分になれた、という表現がふさわしいでしょうか。
そして物語の最後で、彼女は自分の意志である決断をすることになります。
キャロル ―鳥かごに囲われた人妻

舞台は50年代のアメリカ。女性は結婚して子供を産み、生涯夫に尽くすのが幸せであり、それ以外のものを望むことはない、というのが当たり前の時代です。良き妻、良き母を演じながら夫の実家で気取ったランチをし、嘆いていたことでしょう。いますぐここから飛び出して行きたい。でも行くところがない…と。
そんなキャロルでしたが、テレーズに出会ったことで偽りの自分を捨てようとします。
「心に従って生きなければ、人生は無意味よ」
夫と子供のいる家を出て、仕事を見つけ、一人で部屋を借り・・・。
どこまでも、図太く。燃え尽きるまで。
自分らしく、自分らしくって結局どういうことなんでしょうか。すべてを自分の思い通りにすること?いえいえ、それはただの自己中心的な考えですよね。
以前、レズビアンドラマ「Lの世界」についての記事を書きました。その時には触れなかったのですが、あのドラマにも「キャロル」と共通する部分があるんです。それはわたしたちLGBTにとってとても重要な言葉。ドラマの中で登場人物が自ら気付いたり、誰か声かけてくれる、生きるヒントのようなもの。一つだけ、引用します。
「人生は、リスクを負わなければ死んでいるのと同じ」
わたしたちが願うことは同じ。誰かを愛して愛されたいし、マイノリティ(少数者)と呼ばれるのも不本意です。
キャロルやテレーズのように、息苦しい思いをしている人がいたら、ぜひこの言葉を思い出して欲しいです。少しでも自分を解放できますように。
画像出典:collider.com、Fashion Gone Rogue