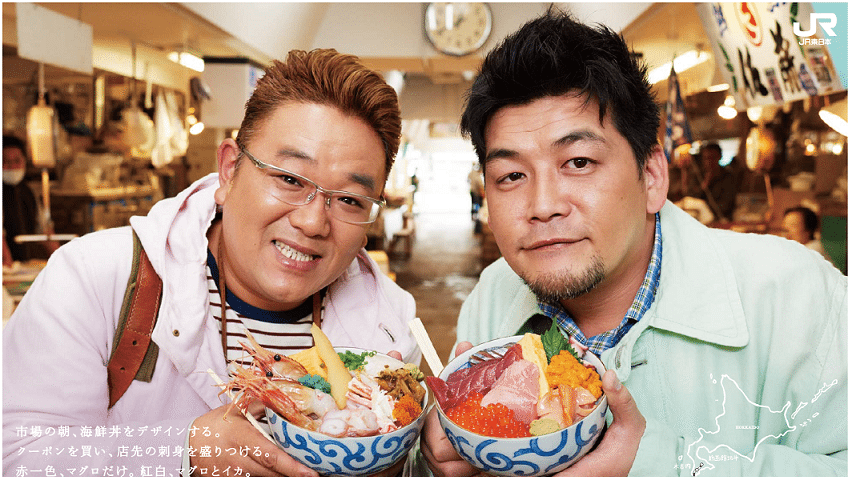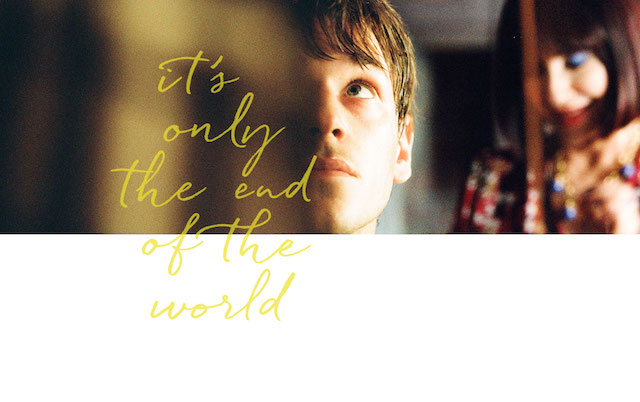自分は十分メソメソしたから、今は強い言葉が必要なんですよ
■LGBTのえらい人に会ってみようシリーズ:1 北丸雄二氏に話を聞いてみる(前編)
ジャーナリスト、北丸雄二氏へのインタビューの後編である。
前編では、以前のツイッターでの氏の発言をめぐる炎上から、改めてご自身の立ち位置についてうかがったつもりだ。それは明らかにまっすぐで、後ろめたさのないものだった。氏から直接受ける印象もまったくその通りの、ざっくばらんで実直なもの。
話の流れの結果だが、後編では氏自身のカミングアウトやプライベートにまつわる、多少くだけた話をうかがった。
『カミングアウト』に対して確固たる意見をお持ちの北丸氏の個人的なカミングアウトは、いったいどういうものだったのだろうか?
世間で言われるホモセクシャルと、自分の中にあるものとが一致しなかった
サムソン高橋(以下”S”):今さら質問ですけど、北丸さんはゲイなんですよね?
「(笑)そこからはじめるんだ」
itaru(以下”I”):北丸さんはぶっちゃけゲイを自覚したのはいつですか?
「僕はいちおう年齢非公開ですけど(笑)、その時代は情報がまったくなかったんですよ。だから、情報集めるために色んな文学から、百科事典から広辞苑まで調べたりして」
S:それこそ同性愛に『変態性欲』みたいな説明が付いてた時代ですよね。
「それに対しては『これは僕のことじゃない』って思ったんですよ。で、自分の中にあるこれを何と言っていいのかわかんなかったんですね。
で、僕はどちらかというとホモソーシャルの人間だったんです。これはつまり、男女の付き合いよりも、普通に男同士の付き合いが好きだったということですね。ここだけの話だけど、自分はずっと女の子と付き合ってたわけですよ。普通にデートもしてたし、まあ、いろいろやってたわけですけど(笑)、でも、付き合ってた女の子とデートの約束があっても、男の友達から遊びに誘われるとそっちのほうを優先して女の子はほったらかしっていうことがままあって。
そのうちに、かわいいと思う男の子ができて。17くらいの頃かな。それが、世にあるいわゆるホモセクシャルなものとどう関係あるのか。その辺のことをずっと考えてた。世にある定義、つまり世間一般から言われるゲイというものと、自分の中にあるゲイというものが、違うわけですよ」
S:僕が覚えているのが、当時なんとかコースとかなんとか時代とか学習雑誌があったんですけど、悩み相談のコーナーで「同性のことを好きになってしまった」という質問がよくあったんですね。で、それに対する定番の答えが「大きくなったら普通に異性を好きになりますよ」というやつだったという。
「僕の時代は、たぶんさらに15年ほどさかのぼることになると思うんだけど、そういう話題すらなかったんだよね。概念がなかった。今のLGBTで言うと、11PM(日本テレビ系で夜11時に放映されていたカルチャー番組)に出ていたカルーセル麻紀くらい? あとは、青江のママ(伝説的なゲイバー「青江」経営者。ゲイ業界で最初に有名になった人物)がメディアには出てて。『自分はこれではないな』、と。当時はそんなもんだった」
I:青江のママとカルーセル麻紀だけを参考にして、高校生が自分のアイデンティティを紐づけするのは難しいですよね(笑)。
「(笑)それで、アンドレ・ジイド(ジッド)が『コリドン』という本を書いているんです。それが何かというと、一大同性愛擁護論ですよ。たしか対話形式の中で、歴史上の同性愛の話をずっと書いている。それを読んで初めて、『これだな』と思ったんです。で、それがなんと、私の高校の図書室にあったんですよ。全集の中にあって。なんで『コリドン』なんか知ってたかというと、なにかで三島由紀夫が言及してたのかな」
S:僕が高校生だった時に、80年代半ばだったから比べたら状況は全然良かったと思うけど、田舎だとやっぱり何も入ってこなくて、代替品として図書室で『禁色』読んでたのと一緒ですね。
「大江健三郎もゲイ小説めいたものを書いてたりするんだよね。三島なんかよりずっと”ゲイ”だった」
S:男性器のことを「セクス」と書いたりとか(笑)。
「大江健三郎は当時同性愛というものを、日常生活から別世界へ突き破るものとして書いてたんですよ。今の可能性ではない別の可能性のなにかとして。架空の可能性として同性愛者を書いてた。それは変態だったり異常者だったりするんだけど。それが時代が変わってくると、彼の同性愛や同性愛者の書き方が違ってくるわけ。80年代90年代に入ってから、今までの書き方を謝るかのように、同性愛者を救いのまなざしで書いている。自分たちの世界に取り入れて、なかなかいい役を与えてるわけ。最近の村上春樹もそうだよね」
S:ベタな言い方だけど、それだけストレートの人の中にもLGBTの意識が入り込んできたんでしょうか。
「意識というよりも、情報ですよ。つまり80年代になにが起こったかというと、エイズの話がものすごく広まるわけでしょ。エイズの話にかこつけて、人権とかカムアウトの話をしなきゃいけなかったり。性的な存在としてのカムアウトじゃなくて、社会的な存在としてのカムアウト。社会の反感を抑えるためには、とにかく表に出て闘わなきゃいけない。陰では闘えない。そんな情報が日本の作家たちをも変えていった」
S:これも陳腐な意見だとは思うんですが、アメリカは闘う相手が続々と出てきたじゃないですか。日本では闘う相手と言われても、ピンとこなかったりするんですよ。しいて言えば、いわゆる「世間様」っていうやつとか……
「でもね、最近その『世間様』というのがネットで形となって出てきてるんじゃないかな。面白い形なんだけど、それってトランプ現象でもあるんですよ。世間様のナマの憎悪とか反感とか差別とかが形になって現出してきている」

幸せじゃない人が増えたときに、それに対しては動かなきゃいけない
I:日本で明確な敵がいないという話ですけど、同性婚をきっかけに見えてきたことがあって。日本で同性婚という言葉が取りざたされるようになったら、はっきりと「認めない」っていう層が出てきたじゃないですか。だから今、敵がちょっと見えてきた時期かな、と思ってまして。アメリカで起きたことは日本でも起きるじゃないですか。だから、同性婚って面白いきっかけだなあと思って。
「さっきも言ったんだけど、物事を止まったものとして見てちゃだめで、必ず動いてる。それがどっちの方向かはわからないけど、遅々として進んでないように見えて、進んでいるんだよ。そのときに例えば個人的なことが政治的なことになってくる。
人間には何が必要か、ってなったときに、家に閉じこもっていつまでも生きていけるわけにはいかない。外に出て、交通機関を利用して、仕事をして、となったときに、自分の個人的な生活にも社会が関わってくることに気付くわけですよ。
例えば家制度ってものがあったときには、レズビアンだろうが誰だろうが女は家にいなきゃいけなかったかもしれない、子どもはお父さんの言うことを聞かなきゃいけなかったかもしれない、お父さんは家のことをなんでも面倒みなきゃいけなかったかもしれない。でも現代ではそれとは違うところで社会を作ってきたわけですよね。それは世の中との付き合い方ということになってくる。例えば人と人が付き合うとなったときに、手をつないで一緒に寝ているだけで幸せだよね、となっても、だったらアパートどうするの、て話になる。
同性婚に対して『それは日本的じゃないよね』ってだけで済ませられない。戦後ずっと続いてきたその『日本的なやり方』というやつがどこかにたどり着いたかというと、どこにもたどり着いてない気がするんだよね」
S:日本では「うやむやに済ませる」という一点になっちゃう気がします。
「うやむやに済ませて、それで幸せだったらいいよ。それでぜんぜん結構。でも幸せじゃないっていう人が増えてきたときには、それに対しては動かなきゃいけないと思うんです」
I:いわゆる日本で言う『隠れホモ』の人たちは、同性婚の話になったときに「日本でそれはそぐわないから養子縁組でいいんじゃない」と言う人が多いんですよ。
「養子縁組でいいならそれでいいんですよ、もちろん。けれど、だからと言ってそれが他の人がしたいと言う同性婚を否定する論理には直接つながらないと思うんだよね。マイケル・ムーアが言ってたんだけど、ストレートの男性に『あなたはゲイマリッジに反対か?』と聞くんだよね。相手が『反対だ』と答える。するとムーアはすかさず『OK、じゃあ、あなたはゲイ結婚しなくていい』って言ってあげるの(笑)」
S:同性婚に関しては、旧来の家制度に絡み取られるだけだから、自分たちのシステムを構築しなきゃいけないんじゃないかっておっしゃる人もいますが。
「それは一理あるんだけど、この圧倒的な異性愛社会において、結婚制度に替わる制度を同性同士でイニシアティヴとってやっていけるのかっていうのがね」
S:そういうシステムを改めて構築するのは現実的にすごく難しいですよね。
「アイディアはあるとしても、それが人の心をなびかせるのはまた別の問題で。また、制度とは別のところで生活を変えていくことはできるから。結局、制度なんてどうだっていいって話もあるんだからね。でも、ここであるものをこちらではダメとする論理にはできないだろって。
個人的なものが社会にとって大切になるのが民主主義だし、自民党が反対している個人主義……これは個人主義が利己主義という言葉に置き換えられているかもしれないけど、それは利己主義とはまったく違って、お互いを尊重する利他主義なんですよ、実は。そういうことまでひっくるめて考えないと、同性婚はただ単に結婚の話になってしまう」

大学の寮で、四年生のときには男の子と付き合ってましたね
I:話を戻しましょう(笑)。世の中にある変態性欲のゲイと自分が紐付けできていなかった17歳の少年が、カミングアウトしたのはいつなんですか?
「僕が公に、一般誌に「ゲイのジャーナリスト」として紹介されたのは1996年のAERAだったかな。それまでゲイ雑誌とかには書いてたけど、もちろん仕事だから新聞にはいろいろ書いてたけど、ゲイだとはわざわざ紹介されてなくて」
S:ゲイを背負ってはなくて。
「(笑)背負ってはないけど、最初のとっかかりは90年に僕が『フロントランナー』というゲイ小説を翻訳したことですね。アカーが『府中青年の家』裁判を起こすちょっと前かな。それまではアウトするも何も、メディアなんて全然なかったんだから」
I:それはメディアの話ですよね。僕らがおうかがいしたいのは、ご自身がおっしゃってた本来の意味でのカミングアウトです。
「いや、それはもちろん当時から認めてましたよ。新聞社内でも目をかけてくれる上司には話してましたし。でも、20歳前後の頃は今でいう『ゲイ』という言葉もなかったんだよね」
S:オカマとかホモセクシャルとか男色とか?
「『ホモ』っていう言葉自体も、定かではないけど70年代に、オカマあたりとは違う、新しいニュートラルな言葉として紹介されたんですよ。薔薇族かなんかだったかな? だから当時の『ホモ』は、差別語でも侮蔑語でもない、その後に出てくる『ゲイ』と同じくすごくニュートラルな言葉だった。話を戻すと、僕は大学四年生の頃には男の子と付き合ってましたね。大学の寮だったんですよ」
I:まあ、素敵な話じゃないですか。それはどういう経緯で?
「寮ってみんな酒飲むんですよ。そこはわりとでかい寮で、いろんな大学のやつらが100人以上いて、毎夜酒盛りするわけですよ。そのうちに、なんか、ねえ」
I:ねえ、じゃないですよ(笑)。大事なところをすっ飛ばしてるじゃないですか。
「後輩連れてって、まあ、かわいいなあって」
I:やっちゃったんですか?
「やっちゃったって(笑)。なんかさあ」
I:向こうもそうだったんですか?
「そうだったんじゃないかなあ」
I:目覚めさせちゃったんじゃないですか? それ、小説にしてほしいですよ。バンカラの時代ですよね。
「(笑)高下駄履いてドテラ着て街歩いてたもんね。そもそも硬派・軟派の硬派って男色のことだからね」
I:そうなんですか!? いい時代ですねえ(笑)。
「軟派が女たらしで、硬派が男色で。だから川端康成が東大生の親に向けてエッセイ書いてんだよね。東大の寮には入れるなと」
I:染まっちゃうからですか。いやあ、10年早く生まれてたら大学の寮に住みたかったわ。
S:ということは、もうその頃には自分の中で自分の指向についてのケリは完全に付いていたわけですね。
「そうですね。ただ、それが社会的にどういう意味を持つのかはいろいろ論争してましたよ。当時の友人と。高校の時は学生闘争の名残の時代だから、性的なものがどう政治的な課題になるかということをバンバン議論して、俺、ケンカしてたもん。でも当時は負け続けてた。だって、『ストーンウォール』も例の『個人的なことは政治的なこと』っていうスローガンも知らなかったし、そんな情報、1ミリも入ってきてなかったから」
S:自分のセクシャリティを絡めつつですか?
「そう。アンドレ・ジイドの『コリドン』を読んだあたりから」
S:それ、ちょっとした「告白」じゃないですか。
「公言してたもん。それがホモセクシャルかどうかわからないにしても、俺、女と付き合うんだったら男と付き合うほうを選ぶよ、って」
I:文字通りの硬派だったわけですね?
「というか、文学少年だったからね。メソメソはしてたんだよ。
I:ちなみに今、恋愛はされてますか?
「恋愛というか、付き合ってるからね、9年。日本にいるときは一緒に暮らしている。付き合うと長いんです。ずっと一緒にいれればいいと思ってます」
I:ああ、やっぱりモテない人の気持ちはわからないタイプですよ。
S:僕らみたいな弱者の気持ちがわからない人ですよ(笑)。
「(笑)違うんですよ。強者になろうと努力してるんですよ。弱者の気持ちはもう十分知ってるから、自分の中でも強者が必要なんですよ」
S:例えば具体的に法を作ったりとか、そういう方向ですか?
「政治なんて嫌いだから茶々入れてるだけだけど、むしろそういうのが好きな人は本当に政治家になればいい。僕は本来は政治的な言葉を使えない。さっきも言ったけど、どちらかというと文学からはじまった人間なんで、でもだからこそプライベートな言葉やパーソナルな言葉というのは、もう十分なわけ」
S:もう十分メソメソした、と。
「(笑)もう十分メソメソしたから、もうそれはわかったから、違うところの言葉が必要かな、と。あと、僕が強面になるのは、強面の相手に対してだけですよ。権力を持たない人に対してはそんなつもりじゃない、……というふうに努めてる、これでも」
I&S:(笑)
「だから僕が文句言ってる相手を自分だと思わないでほしい(笑)」
(この項、了)
失礼な話かもしれないが、思わず「北丸さんって、ゲイですよね?」という質問をしてしまったのは、氏から受ける最初の印象が「ノンケっぽい」というやつだったからである。これは北丸氏を知る複数の方からも事前に同じことをうかがった。ちなみに「ノンケっぽい」というフレーズを使う場合は良い意味と悪い意味があるのだが、氏の場合は圧倒的前者に当てはまる。
私が事前に想像していたことを告白する。それは意地悪ながらも、「ひょっとしたら新聞社という男社会でノンケ的/マッチョ的にふるまわなければならなかったのではないか」というものだった。氏の(こういう言葉を使うとLGBTメディア的にどうかと思うが)自然な男らしさは、ゲイ的なものへの恐れからではないか、と思っていたのだ。
それはまったく見当はずれだった。
話をうかがいながら、「ああ、こりゃノンケっぽいのも当然だ」と思ったのは、北丸氏のプライベートも、氏の経歴や政治問題を見つめるまなざしと同じようにまっすぐだったからである。学生時代に自分のセクシャリティを悩み探りつつ確立して、日常生活の中で恋人も見つけている。ゲイである自分への後ろめたさはみじんもない。率直に、うらやましい話だ。
だから北丸氏はLGBT界隈で批判されることも多いのかもしれない。トラウマがあって後ろめたくてジメジメしたところからの言葉のほうが私たちには簡単に届きやすいのである。
ただ、最後で明かされたように、その強い言葉は文学少年時代のプライベートでパーソナルな自分を土台として発されるということは覚えておいたほうがいい。
切り傷をふさぐかさぶたのように、それには優しさが含まれているはずだ。
(文責/写真 サムソン高橋)
北丸雄二
毎日新聞記者、中日新聞(東京新聞)ニューヨーク支局長を経て1996年に新聞社を退社。現在はフリーランスとしてニューヨークでコラム、時事評論、芸術評論など多岐にわたって著述活動を続ける。日米を軸とした社会、政治報道に関わる一方で、20年以上前から日本でただひとり継続的・体系的に世界のLGBT関連ニュースを提供してきたジャーナリスト。
北丸雄二のNew York Jounal “Daily Bullshit”